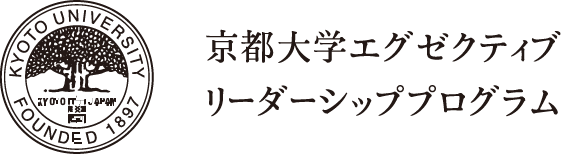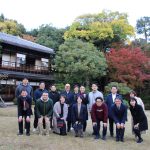2015年10月24日、午前は農学研究科の阪井康能先生による『農芸化学(応用微生物学・応用分子細胞生物学)』の講義でした。酒類の発酵に関する視点を通じて、人類がいかに微生物を活用してきたかを歴史的にたどり、抗生物質のスクリーニングや化学工業など最先端の技術への応用について講義をしていただきました。身近な問題である遺伝子組み換え食品に関して、受講生との間で議論が交わされました。

モデレーターは櫻井繁樹先生が務めて下さいました。

午後の講義は、三枝成彰先生による『なぜ西洋音楽は、世界標準になれたのか?』でした。
譜面に書き起こされることによって、再演可能性を獲得したことが、西洋音楽の世界標準たるゆえんであることを説かれました。モーツァルトとベートーヴェンの違いについて、宗教と音楽についてなど、西洋音楽のあらゆる側面についてお教えいただきました。

講義はピアノ演奏やオペラの映像視聴を交えて行われ、受講生は実際の音に耳を傾けました。

モデレーターは山口栄一先生が務められました。三枝成彰先生の代表作のひとつである、オペラ「KAMIKAZE-神風-」について解説をしてくださいました。