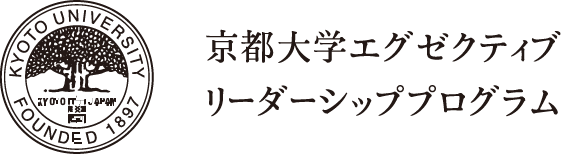2023年12月2日
自動車メーカー グループリーダー
粟野 通期で受講していただきましたが、特に印象に残った講義をお教えください。
受講生 金出武雄先生の講義が印象に残っています。成功するアイデアは単純であるということ。一方で、普段の雑務などもスキルをもって愚直にやらないといけないということ。金出先生の理念である「素人発想玄人実装」を、私も普段の業務でやらなければならないという心構えができました。

一方、感覚を研ぎ澄ませて、 感じたことを一般化、標準化、言語化する上原麻有子先生の哲学の講義も衝撃がありました。「行為的直観」という考え方はものづくりに通じるところもあると思います。哲学の話をされているけれど、客観的に見たら、自分の今取り組んでいる仕事に応用できてしまう。物作りって、思いを作る側面がありますから。
1つ1つの講義に学びがあるというのがELPのすべての講義を通じての気付きです。こんな風に、語りはじめたら時間がなくなってしまいます。
粟野 ELP全体のプログラムについてどういう学び、経験を得られましたか。ご自身のお仕事や人生にどのように繋がるでしょうか。
受講生 1人の先生について1個でも真似しようとを決めて授業を受けているのですが、すべての先生に共通してるところが 3つあると思っています。1つは務本。ELPのテーマですが、日常の言葉で言えば原理原則ですね。それをちゃんと理解した上で研究や作品作りをすることの重要性。基礎があるからこそ、技術を応用して、組み合わせて、大きな成果が出ているんだなという発見がありました。2つ目はハードワーク。一流の先生方は自分を追い込んで仕事をしている。誰よりもすごい手数で行動しています。3つ目は、みんなそれを楽しんでいる。この3つが共通していて、自分でもやっていかないといけないという気づきであり、活かさなければならない点です。
粟野 これから参加される方へのメッセージをお願いします。
受講生 私はMBAも取得していますが、そこでの学びとは全然違います。即効性を求めるならMBAに行ったほうがいいと思いますが、ELPで学ぶことの本質はそこにはありません。小手先の技術や最新の技術を組み合わせて、時代の流れに応じて成果を出すことは、なんとなくできてしまうのですが、振り返ってみて何か残ってるかというと、残っていなさそうな気がしていた数年間だったんです。原理原則と本質をしっかり学べば、なにか変化があったときにも、すぐに応用できる。これがELPを通じての気づきであり、学びであり、心がけないといけないことだと思います。
粟野 振り返って、何か残ってるかどうかっていうのは、とても印象的ですね。
受講生 先生方も手数を打って打って、多分失敗してるものもいっぱいあると思うんです。それも含めて振り返ってみて、成功した成果だけを成功と言えるのであって、その成功の基礎にあるのは小手先でやったことではないもののはずです。
ELPでは「なぜ」を突き詰めて問いを考えます。例えば、AIがものすごく変化しているこの時代、AIとどう共存するかが課題になっているときに、小手先の技術は全部AIに代わってしまい、残るのは本質的なところだけだと思います。その学び方を学ぶ。それを学ぶためには本物の先生に触れないといけませんね。百聞は一見に如かず、頭でっかちではなくて生の体験を重ねることによって、人生がより豊かになってゆくのだと感じています。
粟野 ありがとうございます。では最後に、あなたにとってELPとは。
受講生:自分自身と、 自分を通じて関わる人たちの人生をより良くするための学びの場です。ELPは答える力より問う力を鍛える訓練の場、問い方の質を上げる場です。 本物の先生に聞くからこそ、反省もあるし、フィードバックもある。その問いの質が上がると、自分の問い方、考え方が変わって、未来が変わるし、見え方も変わって、世界観が変わってくるので、それは自分にとってもプラスになるし、その問いを発信することによって、周りにも気づきを与えるっていう意味で、自分発信による、周りをより幸せにするための訓練の場みたいな感じだと思います。
これまで、枝葉は学んできたけれど、枝だけではだめだったんだと感じた1年でした。このELPでの学びを、修了してからどう鍛え続けるか、年輪みたいにちょっとずつ大きくできるかが今後の課題です。
40、50代の方が参加されれば、これまでを振り返ることができたり、意思決定するための考え方を学んだりすることができます。それも重要な一方で、20代後半30代前半くらいの年齢の人たちに若い段階で気付かせることによって、その人が10年後に役職につくための早期訓練になる可能性も大きいと思います。
粟野 どうもありがとうございました。