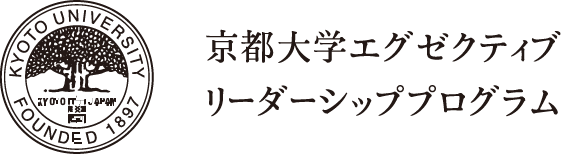上原 麻有子
UEHARA Mayuko
京都大学大学院文学研究科 教授
講義概要
「哲学」という学問は、日本では近代の黎明とともに西洋哲学を翻訳により導入することで開かれた。1930年代早くも、西洋最先端の哲学に決して引けを取らない、日本独自の哲学的立場を確立するに至ったのである。京都学派はその役割を担う代表的な知の集団であったと言える。講義では、学派の思想基盤となった西田幾多郎の哲学に焦点を当て、西田による「物を作る」ための技術論を紹介する。また、準備している課題は次の3つである。1. 西洋近代の哲学的パラダイムの乗り越え、2. 人間関係と社会・環境・世界の多様性に基づく西田的技術知の内実、3. 物作りの現実。「物となって見、考え、行う」哲学は、今後の私たちの世界に何か貢献し得るのであろうか。受講される皆様とともに考えてみたい。
世の中をどのように変えるのか、どんなインパクトがあるのか
京都学派や西田の哲学が、経世済民であるとは言い難い。しかし1930-40年代、日本が完全に世界に組み込まれた現実のもと、哲学者たちは個人と全体(社会・環境・世界)の複雑に入り組み、矛盾の内在する関係性を、そういうものとして論理化した。あの昭和の歴史はまだ現代の社会・文化の土台としてリアルに生き続けている。パンデミック、地球環境の激変等により、私たちの世界観は大きく変わろうとしている。技術知は、当時の哲学者たちの予測を大幅に超えて、私たちの生活に幸福と危険の計り知れない矛盾をつきつけている。マニュアルはもう通用しない。しかし、やはり世界変革の歴史を生きた彼らの哲学は、それを更新し続ける思考の深め方、知恵を提供してくれるのではないか。
講師プロフィール
経歴
京都大学大学院文学研究科教授。総合地球環境学研究所上廣環境日本学センター客員教授。Journal of Japanese Philosophy (ニューヨーク州立大学出版) 編集長。西田哲学会理事、同学会編集委員長(2021-2024年)。日本学術会議連携会員。専門は、西田哲学、京都学派を中心とした近現代の日本哲学、翻訳哲学、女性哲学。フランス国立社会科学高等研究院博士(哲学・翻訳学)。
著書
共著『近代人文学はいかに形成されたか 学知・翻訳・蔵書』勉誠出版(2019年)、共著『危機の時代と田辺哲学』法政大学出版局(2022年)、共著『問いとしての尊厳概念』法政大学出版局(2024年)。