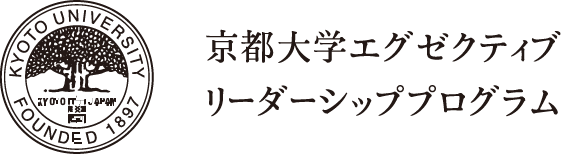西村 卓也
NISHIMURA Takuya
京都大学防災研究所附属地震災害研究センター 教授
京都大学防災研究所 副所長
講義概要
2025年1月15日に南海トラフ巨大地震が今後30年間に発生する確率が約80%であることが、政府の地震調査委員会から発表されました。地震の予知に関する研究は、昔から取り組まれてきましたが、地震の予知が実現する見込みは立っていません。一方で、地震発生の日時を特定しない長期的な予測は、南海トラフ地震のように現在でも地震調査委員会により実施されています。本講義では、このように現在行われている地震の長期予測に関して手法や予測結果について解説するとともに、地殻変動データなどを用いた新たな予測手法に向けた研究の現状についても紹介したい。
世の中をどのように変えるのか、どんなインパクトがあるのか
南海トラフ巨大地震が発生すれば、西日本の広範な地域において、地震や津波による大災害が発生することが確実視されている。将来発生する災害を軽減するためには、地震がいつ頃起こりそうかだけなく、どの地域にどの程度の規模の地震が発生するのかを想定して、対策を進める必要がある。日本列島では、人工衛星を用いて自分の位置を正確に測定することができるGNSS観測網が展開されて30年が経過し、日本列島の地殻変動を把握するために大きな成果を挙げており、その中には地震の長期予測に役立つ成果もある。この研究では、GNSSを用いた地震の長期予測に関する研究、特に現在活断層調査だけに基づいている内陸地震に対する予測手法を高度化して、予測精度の向上を目指す。
講師プロフィール
経歴
1972年、北海道生まれ。1997年東北大学大学院理学研究科博士前期課程修了後、建設省(現、国土交通省)国土地理院に入省。同院地理地殻活動研究センター研究員、主任研究官など歴任する中、2002年には文部科学省宇宙開発関連在外研究員と米国地質調査所にて研究を行う。2013年より京都大学防災研究所准教授、2023年より教授。2024年より防災研究所副所長。博士(理学)。学生時代より一貫してGNSSデータなどを用いた地殻変動の解析により、地震発生メカニズムの研究を行う。現在、政府の地震調査委員会、同長期評価部会、南海トラフ沿いの地震に関する評価検討会の委員を務める。受賞歴は、日本測地学会坪井賞(2010年)、日本地震学会論文賞(2013年、2016年、2024年)。